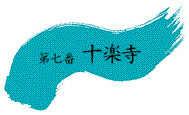
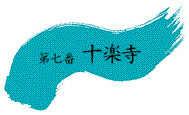
 |
 |
 |
弘法大師はこの地から3km奥
の谷間、今の十楽寺谷で阿弥陀如
来を感得され、樟の木を刻んで高 さl9mの阿弥陀如来坐像を造り、ご
本尊として十楽寺を開かれ、人間 の持つ8つの苦しみをのがれて極楽
浄土の10の楽しみを得られるよう との願いを込めて光明山十楽寺と
号し、第7番の霊場に定められまし た。 その後、長曽我部軍の兵火にか かって焼失し、寛永12年(1635)現
在地に変りました。 当時の本堂は葺ぷきのささやか
な建物でしたが、明治に入ってか
ら現在の本堂に建てかえられまし た。 |
6番札所、安楽寺と同様に、おと ぎ話に出て来る竜宮城を思わせる 美しい朱ぬりの鐘楼門をくぐり、 石段を上ったところに中門があり ます。中門をくぐりぬけると、 広々とした境内には見事な老松が 生い茂り、その向うに山を背にし て見事な本堂が建っています。本 堂の右手には方丈、客殿があり、 本堂前から左手の石段を上ると一 段と高いところに大師堂がありま すが、いずれの建物も四国88力所 にふさわしい、風格のあるたたづ まいを見せています。 このあたりは土御門上皇の行在 所のあった所といわれ、もとは御 所村と呼ばれていました。 上皇は承久の乱(1221)によって 土佐の幡多に流され、その後阿波 の国で8年間を転々とすごされて、 37歳の若さで自刃された、不過な 上皇であります。 |